国民健康保険税の納付について
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が国民健康保険以外の医療保険に加入している場合も国民健康保険税の納税義務者となります。
国民健康保険税の課税対象となるのは国民健康保険の加入者のみですが、納税通知書や納付書等は納税義務者である世帯主あてにお送りします。
また、国民健康保険税が未納となった場合の滞納処分の対象も、納税義務者である世帯主となります。
国民健康保険税の納め方
国民健康保険税は資格を得た月から納付します。
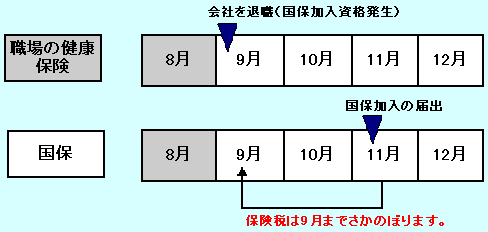
年度の途中で国民健康保険の加入者に異動があった場合は、国民健康保険税を月割りで再計算するため、年度の途中でも税額が増減します。そのときは、「国民健康保険税納税(変更)通知書」で変更内容をお知らせします。
国民健康保険の加入者及びその世帯主は所得申告が必要です。
国民健康保険は、加入者及びその世帯主の所得に応じて、国民健康保険税の軽減判定や高額療養費の自己負担限度額の判定を行います。
所得がない方など確定申告をする必要がない方でも必ず市・県民税申告書にて申告してください。海外在住者は、申告様式を送りますので連絡してください。
申告がないと、国民健康保険税の軽減措置が適用されない、高額療養費の自己負担限度額が高くなるといった不利益が生じる場合があります。
国民健康保険税の納期は年間8回です
国民健康保険税は、加入者の前年中の所得などに規定の税率をかけて1年分の税額が算出されます。
前年中の所得が確定した7月の時点で年税額を計算し、8回の納期で納めていただきます。
なお、各期の税額に1,000円未満の端数が生じたときは、1期に算入します。
国民健康保険税の納期は年間8回です(下表参照)。納期限日はそれぞれ月末です(12月のみ25日)。ただし、月末日及び12月25日が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日が納期限になります。
|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- |
- |
- |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
- |
年金からの天引き(特別徴収)の方は納期が異なります。
年金天引き(特別徴収)については、下記のページをご覧ください。
納付方法について(納付書・口座振替・特別徴収)
納付書
納税通知書に同封されている納付書で、納期限までに取扱金融機関等の窓口で納めてください。納付場所については納付書裏面をご覧ください。
コンビニエンスストアでは、バーコードの無いもの、納期限または使用期限を過ぎたものはお取り扱いできません。
また、各期の納付額が30万円を超える場合もお取り扱いできません。
口座振替
国民健康保険税は口座振替がおすすめです。
国民健康保険税をご指定の口座から振替できます。一度お申し込みいただければ継続して各納期限の日に指定口座から自動的に振替納付することができます。
口座振替の手続きや利用できる金融機関については、下記のページをご覧ください。
国民健康保険税の口座振替手続きをするときの注意点
国民健康保険税の「納税義務者」は世帯主です。
振替口座の名義人はどなたでも登録できますが、
口座振替申請書の納税義務者記入欄(用紙の中ほど)には、世帯主の氏名を記入してください。
国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
特別徴収は、世帯主が受給している年金から、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に分けて、国民健康保険税を差し引く(天引きする)制度です。
対象になる条件や納付方法については、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。







更新日:2025年05月07日