自転車の交通安全
多様な用途・目的で幅広い年齢層に利用されており、エコで健康的な交通手段として近年さらに利用ニーズが高まっている自転車ですが、みなさんしっかりルールを守っていますか?
「自転車は車両の仲間です。乗れば車両、降りておせば歩行者」
令和4年11月1日から新しい自転車安全利用五則が適用されることになりました。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
自転車の通行方法等に関する主なルール
通行場所・方法
車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
歩道における通行方法
自転車が歩道を通行する場合は、道路標識等により自転車が通行すべき部分として指定された部分(自転車通行指定部分)がある場合は当該部分を、指定されていない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
ただし、自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
歩行者用道路における通行方法
道路標識等によって車両の通行が禁止されている歩行者用道路を警察署長の許可を受け、または禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従う。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。
自転車の乗り方
安全運転の義務
ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
二人乗り等の禁止
小学校入学前の子供を乗せる場合等には、各都道府県公安委員会規則において定められている自転車の乗車定員に反して、自転車を運転してはならない。
並進の禁止
「並進可」の道路標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
ブレーキ不良自転車の運転禁止
基準に適合する制動装置を備えていないため、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
傘さし運転の禁止
傘をさして自転車を運転してはならない。
自転車に傘を固定する器具を使用している場合でも、傘さし運転とみなされる可能性がある。
イヤホン・ヘッドホンの禁止
イヤホンやヘッドホンを使用し安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で運転してはならない。
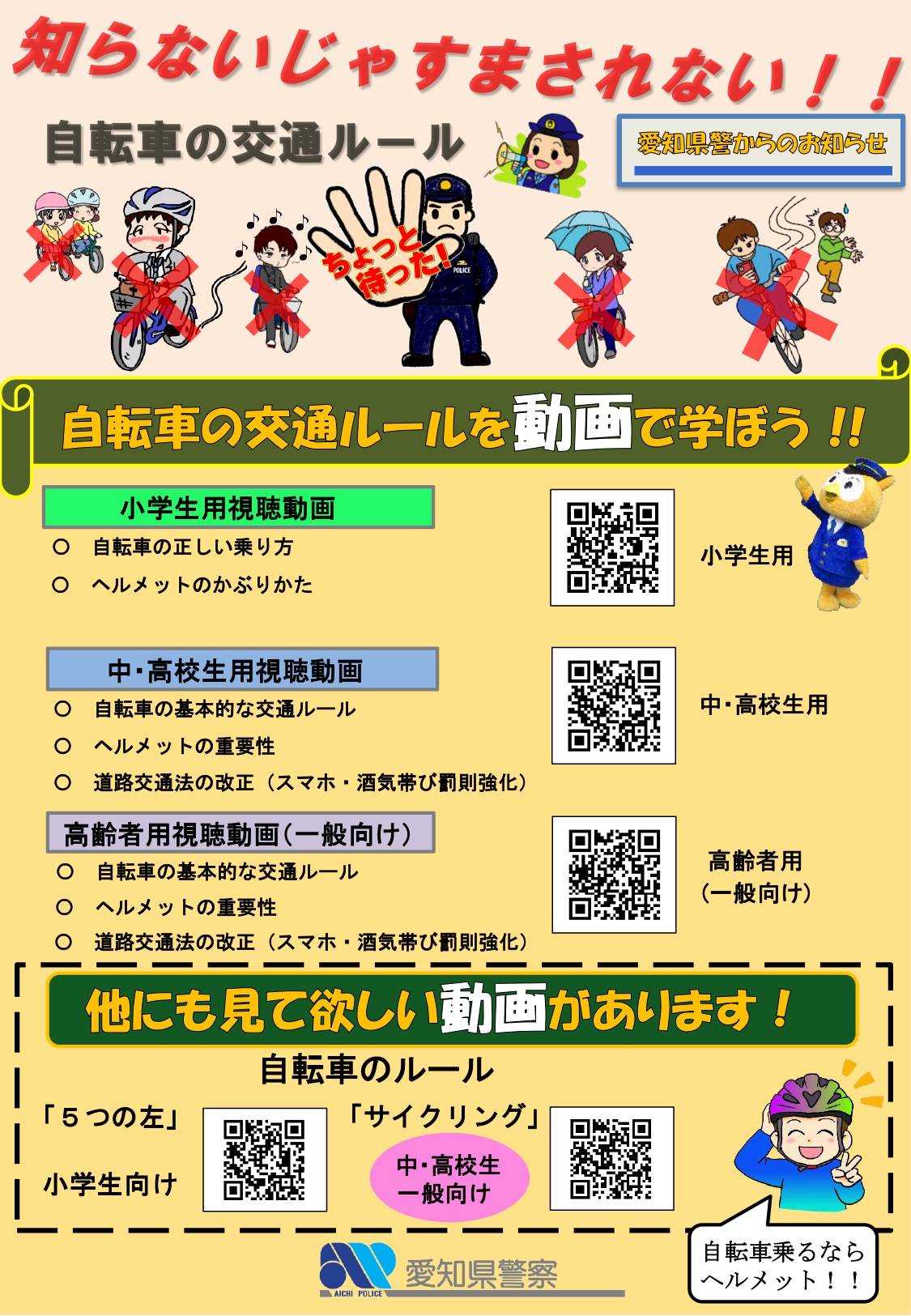
「自転車運転者講習」の受講が義務に
平成27年6月1日から、飲酒運転や一時不停止、信号無視など、特定の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
自転車運転者講習受講の対象となる危険行為は次のとおりです。
- 信号無視
- 遮断踏切立入り
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
- ながらスマホ
自転車運転者講習チラシ (PDFファイル: 875.6KB)
・令和6年11月1日 自転車に関する罰則が整備されました
運転中のながらスマホ禁止
禁止事項
・自転車の運転中、手に保持しているスマホでの通話
・スマホ画面を注視すること
罰則内容
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合→6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
罰則内容
- 酒気帯び運転 ・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合・・・自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合・・・酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合・・・同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
この記事に関するお問い合わせ先
くらし文化部 安心安全課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1
電話番号:0561-56-0611
ファックス:0561-63-2100
メールフォームによるお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。







更新日:2024年12月05日